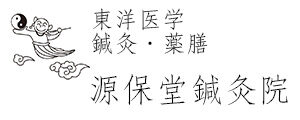お灸についてのQ&A
こちらのQ&Aでは、お灸についてのよくある一般的な質問とその答えをまとめております。
源保堂鍼灸院で行っているお灸の解説は、「源保堂鍼灸院の鍼灸についてのQ&A」にまとめてあります。
お灸についてのご質問
ご注意点
以上の内容は、これまでの治療実績や、患者様からのご感想などを基にまとめておりますが、効果の出方や治癒までの期間、また効果があるかないかなどは個人差もあることをご了承ください。期間や効果の目安もまとめたページがありますので、そちらを併せてご覧になってください。
また、こちらは源保堂鍼灸院のサイトですので、当然ながら当院の鍼灸治療の特長を挙げておりますが、他の鍼灸院との優劣を書いたものではないことをご了承ください。あくまで、あまたある鍼灸院の中から自分に合ったところを見つけるための情報の一つとしてお読みいただけたらと思います。当院の鍼灸が、患者様の好みも含めて不向きな方もおりますので、そのときは他の鍼灸院をあたってみてください。
日本の鍼灸師はみな勉強熱心で、それぞれに特徴を持った施術をしており、国民の健康のため日夜努力している存在ですので、基本、どこの鍼灸院へ行っても間違いはないと思います。鍼灸院は、自分の体と心を預ける場所ですので、ご自身に合った鍼灸院が見つかるようお気軽にお尋ねすることをお薦めいたします。
皆様にとって、心から信頼できる鍼灸院が見つかることを願っております。