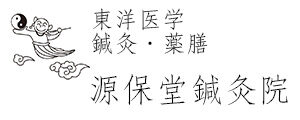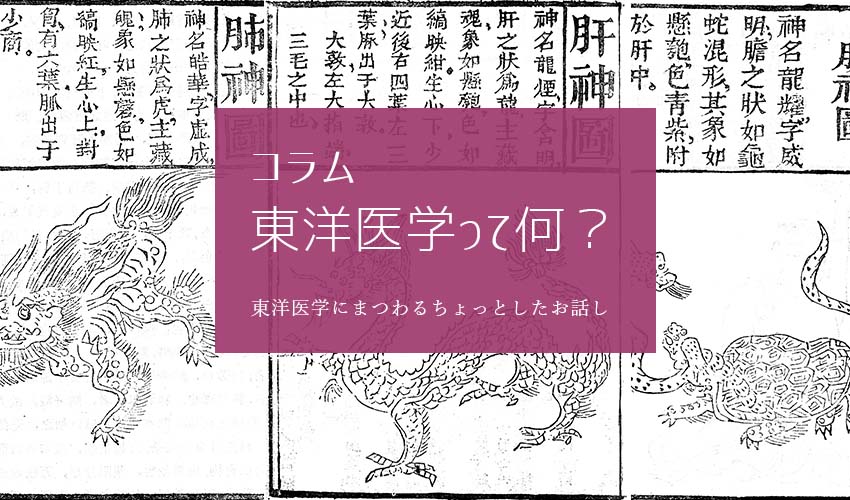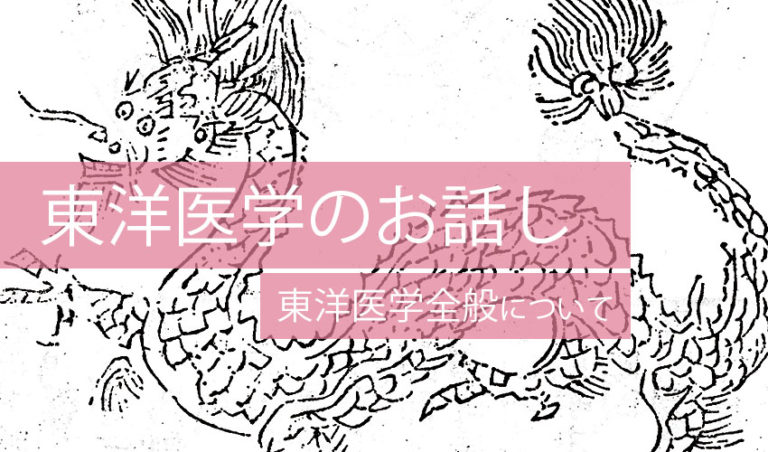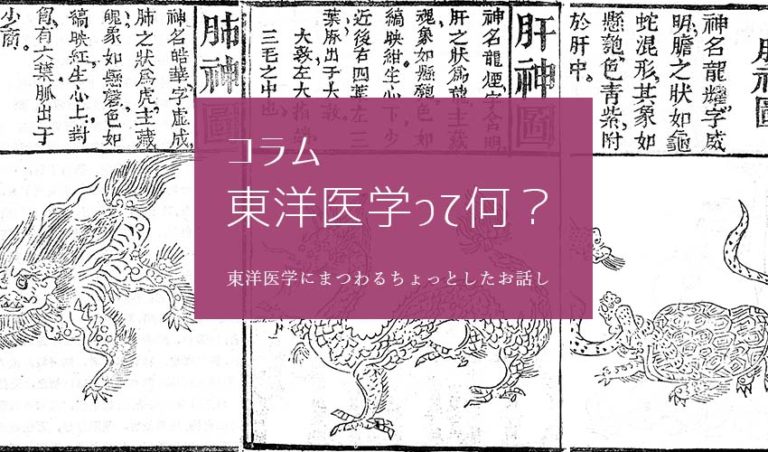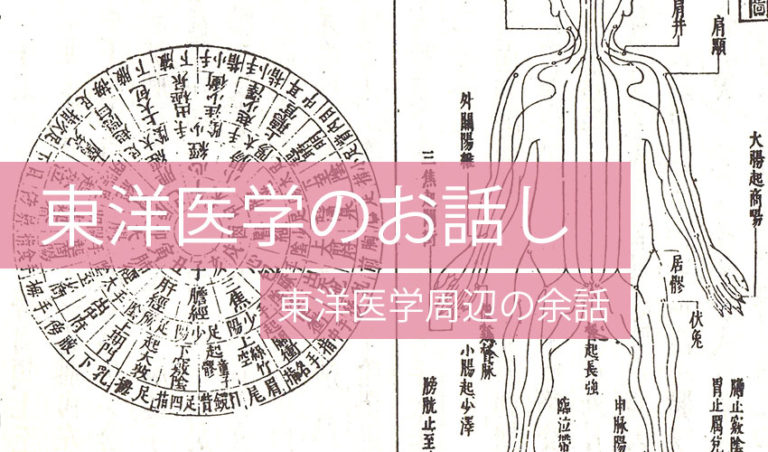花粉症のこと
年を明けるとそろそろ花粉が飛んできます
年末の慌ただしさを過ごし、やれやれと思って年始を迎えることになりますが、ホッと一息ついて気が抜けると風邪をひいたりしてしまいます。食事も不規則になるのも重なります。
しかし年が改まると、不思議と気分も改まって気持ちも穏やかに。
春の訪れは冬の終わりでもあり、自然界も明るさを増し、気持ちも華やかになっていきます。
でも、花粉症の方にとっては憂鬱な季節の始まりでもあります。
そしてこの季節になると「花粉症は鍼で治りますか?」という質問を受けることも多くなります。
これまでのこのコラムを読んでいただいた方にはもうお分かりと思いますが、「花粉症に効くツボ」があるわけではありません。
が、東洋医学の知識を使って生活していただくと、花粉症が軽くなって無事に過ごすことができることも多くあります。
東洋医学では、体の周りを守ってくれる衛気というものを想定しています。
これは、体の外からやってくる様々なものから身を守ってくれますので、花粉にも衛気の強さが必要になります。
花粉がたくさん飛んでいても、それらが体の中に入らないようにキャッチできるかどうか、それが衛気の強さという事になります。
また、衛気だけではなく、津液・営気という体の中を巡っているものの状態も順調であると、より望ましいと考えます。
この衛気は、現代医学でいうと、ひとつには粘液と考えることもできます。
花粉症の解釈にはいろいろありますので、それらを一つ一つ考察していかなくてはいけませんが、ここでは“粘液”の強弱と考えて、「花粉症は粘液不足」によって起きると言うことができます。
鼻にある粘膜が、しっかりした粘着度のある粘液を出すことができれば、粘液が花粉をキャッチして花粉が身体に入りませんので、花粉症は起こりにくくなります。逆に粘液が弱いということは、花粉がキャッチされないので、身体の中に花粉が入り込みやすくなるので、粘膜を刺激してくしゃみや目の痒みを引き起こすという花粉症の症状が起きることになります。
では、どうして粘膜の粘度が落ちるのでしょうか・・・?
これはやはり生活習慣、特に食べ物の影響が少なくありません。
冷たいものや甘いものの食べ過ぎ、そしてたんぱく質の摂取不足などが考えられます。この点を注意しながら生活習慣を変え、そして同時に身体の中の栄養が巡り、代謝が良くなるよう鍼灸治療受けますと、花粉症は改善されていきます。
さらに、そういった生活習慣だけでなく、同様に注意を払うべきなのは、季節の過ごし方です。春の前には当然冬が来ますが、冬にどういう生活をしたかによって春の体質が決まってきます。これは、冬にじっとしていた種が、春に発芽するのと同じことです。冬の過し方が悪かった場合、種はいい状態ではないので、春の良い状態での発芽は期待できません。この季節の流れを考えて見ますと、春にどういう過ごし方をしたかで夏の体質が決まり、同じように秋、冬と順番に繋がっていき、そして再び春を迎える・・・。このように、季節には切れ目はないので、今現在ある体質を気を付けないと、身体は悪循環のまま進み、悪い影響を次の季節に持ち越してしまうことになります。
以上のことを考えてみますと、花粉症が出始めたときに治療を始めたのでは、体質改善にはちょっと遅いところがあります。できるだけ早い段階(可能であれば1月頃から)での治療を継続的に受けていただき、そして食事に気をつけて、春に向けての身体づくりをすることが大切になります。もちろん花粉症になってから来ていただいても身体は治る方向に向かいますので、治療を受けていただけらば、それ相応に症状は軽くなります。しかし、できるだけ早め早めの対処によって、花粉を身体に入れないように防御することをお奨めいたします。
季節は切れ目がありません。そして身体もその季節に沿って生きて、生かされています。花粉症のような季節の病を診ていると、特にそのようなことを感じることができます。
花粉症に効く飲食物(個人差がありますが、参考にしてみてください。)
粘り気のあるもの
納豆、めかぶ、オクラ、カスピ海ヨーグルトなど
身体を温め免疫を調える
長ネギ、にんにく、レンコン、たまねぎ
その他補助的なもの
甜茶、杜仲茶、しそ、ネトル(ハーブティー)など
花粉症に効果があるといわれる漢方薬
上述しましたように、体の外側を守ってくれる衛気を強くしてあげることが花粉症対策になるわけですが、その衛気を強くしてくれる漢方薬が、玉屏風散というもの。
当院では、玉屏風散と同じ構成で作られた衛益顆粒というものを販売しております。
風邪の予防にもなりますので、まだ寒い冬のうちから飲んでおくと風邪と花粉症、冷え性などの対策にもなって、とても重宝いたします。
漢方薬は、証というものを立てて、より的確なものを考えることが大切ですので、どうしても来院していただく必要があります。
漢方薬のご相談は随時受けておりますので、いらっしゃるときはお電話でもいただけると助かります。
衛益顆粒についてはこちらのページをご覧ください。