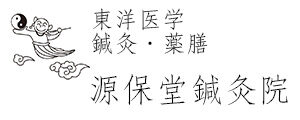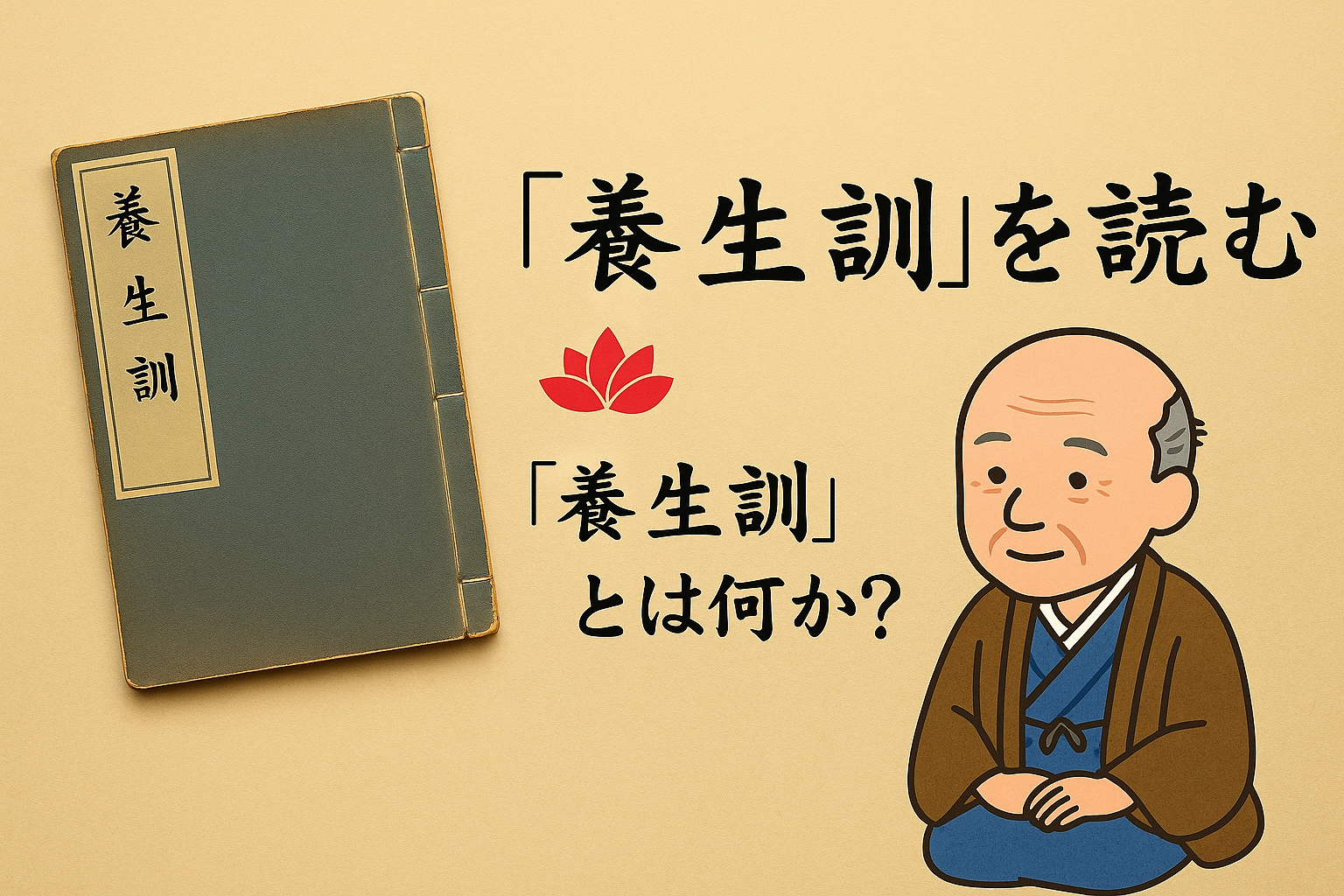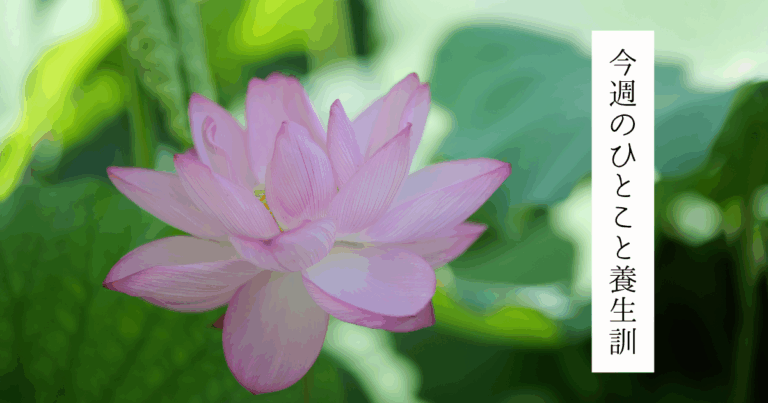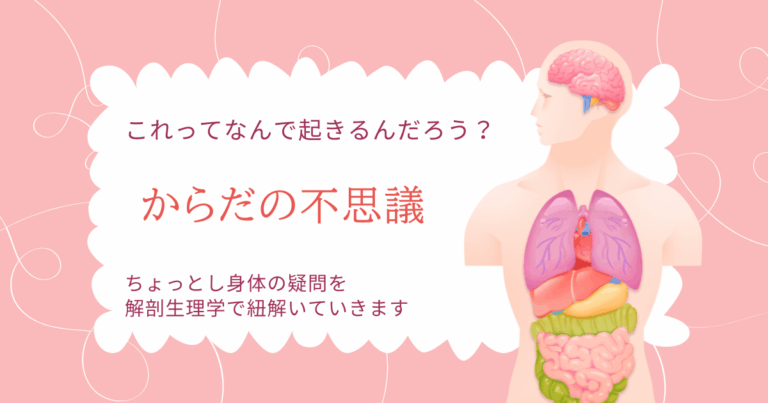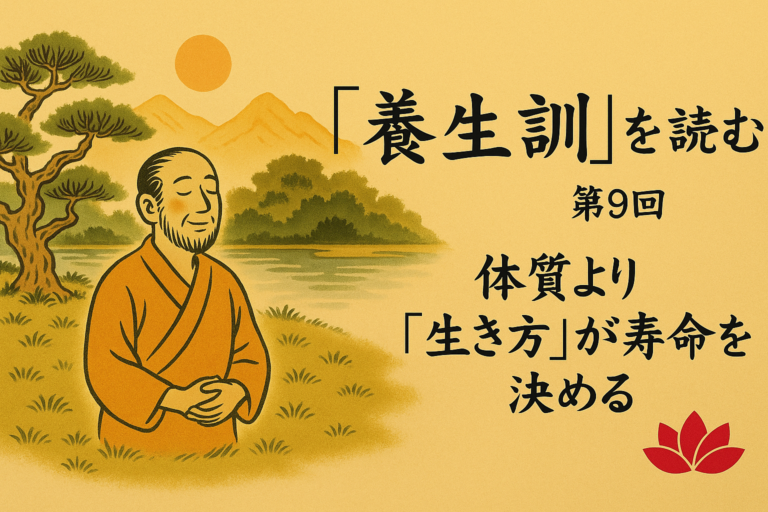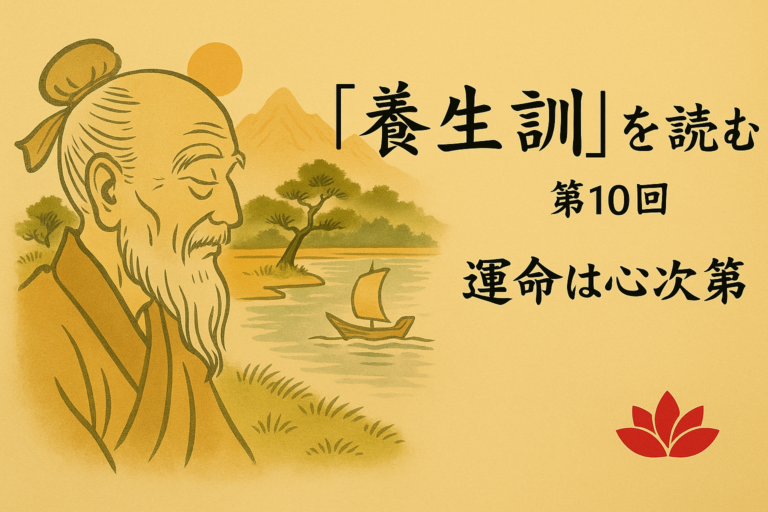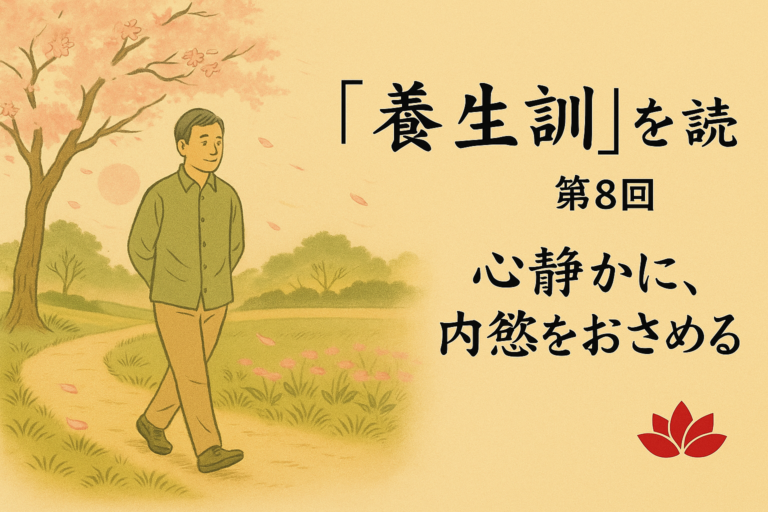『養生訓』を読む 第1回
『養生訓』を読んでみよう
鍼灸師になりたての頃、いや、鍼灸学校に通っている頃だから、正確にはまだ鍼灸師の卵だった頃のこと。私は、とある鍼灸の流派の勉強会に通っていた。今は辞めてしまったけれど、当時はとても勉強になるものだと確信し、それを修得するために2年は通っただろうか。その後、その勉強会の鍼灸手技はしばらく使っており、今でも時折その考え方は参考にしている。
この勉強会は、『黄帝内経』をはじめとする古典医学書をダイジェスト的に紹介し、解説してくれたのですが、その一冊が、今回から当ブログで解説する貝原益軒(1630-1714)の『養生訓』でありました。江戸時代に書かれた本が、今でもこうして読めるんだなと、他の古典医学書の時もそうだったけれども、それらと同じように、新鮮に驚いて魅了されていたのです。
もちろん『養生訓』は江戸時代に書かれた本でありますから、いくつか修正しなくてはいけないところもあるし、個人的な見解とは異なることも多々ある。しかし、それ以上に、この現代にも通じるものがたくさん含まれているので、賛否両論、私の意見も入れながらご紹介していこうかと考える次第です。
いつものように筆は遅いのではございますが、お付き合いいただけたらと思います。
『養生訓』とは?
『養生訓』の成り立ち
『養生訓(ようじょうくん)』は、江戸時代の学者、今でいうエッセイストでもある貝原益軒によって著されたもので、その内容は、健康で長生きするための心得となっています。出版は1713年(享保元年)で、なんと益軒が83歳(益軒がなくなる前年)のときに著したもので、まさに自らの体験と実践に裏打ちされた“人生の集大成”です。江戸時代は300年の太平の世のもと、出版文化が花開き(NHK大河ドラマ『べらぼう』でも描かれている)、数多くの書物が世に出されました。そのうちの一冊が『養生訓』だったわけですが、その中でも群を抜いて多くの人に読まれたベストセラーであり、現在も日本の古典の代表として文庫本で簡単に手に入るものとなっています。
前述したように、『養生訓』は益軒がなくなる前年に出版したものであります。想像するに、自分が生きてきて長い道のりを振り返り、あれはいい、これはいいなど、いろんな角度から考察したに違いないのであります。健康について書かれた本だからといって、単純に医学的な話だけではなく、儒教的な立場からも生命の存在意義を説いてます。そしてその根底に流れるものは、自分と向き合いながら歩む姿勢、狭義の意味では、奥さんを愛する心にあるのではないかと思います。
そこで、次に貝原益軒について見てみようと思います。
『養生訓』の内容・構成
『養生訓』は、以下のようなテーマについて具体的に述べられています:
- 食事・睡眠・運動といった生活習慣
- 感情や欲望のコントロール
- 老いとの向き合い方
- 医療や薬との付き合い方
- 人間関係や心の在り方 など
全体は「巻之一」から「巻第八」まであり、まさに今でいう健康指南書・健康医学書+人生哲学書+予防・未病医学書といった構成になっています。
著者、貝原益軒について
貝原益軒は、“寛永通宝”でお馴染みの寛永の七(1630)年に、筑前(福岡県)の黒田家の下級武士の家に生まれました。名前については、名は篤信と言いますが、柔斎、損軒などと号し、晩年に益軒と改めています。
19歳の時に黒田家に仕官しましたが、すぐに免職となって7年間の浪人生活を送ります。この間、江戸に出て医者を志すも、学識が認められて27歳で再就職し、71歳まで藩士兼学者としてその職を全うしました。益軒は小さい頃から苦労を重ねてきましたが、『養生訓』を読みますと、その分、家を大事にし、勤勉第一、生活も慎ましやかに、そして身体を大事に日々を重ねてきた様子が伺えます。
益軒の著書としては、今回ご紹介する『養生訓』が最も有名ですが、人生の楽しみを説いた『楽訓』や、故郷の地誌である『筑前国続風土記』、そして博物学の百科事典として『大和本草』というものを著しており、儒学者としてだけではなく、科学者としての一面もありました。こういった著作物からも分かるように、『養生訓』は、当時の科学的な見解も含めた養生書であることを察することができます。
なぜ今、『養生訓』なのか?
江戸時代に書かれたこの本が、300年以上経った今でも読み継がれているのはなぜでしょうか?
それは、
- 「健康は自分で守るもの」
- 「心と体はつながっている」
- 「欲望や感情を整えることもまた養生」
という、現代にも通じる根源的な知恵が詰まっているからです。
そして何より、益軒はただの理論家ではなく、自ら実践して、実感をもって書いていることが伝わってくるからこそ、心に響きます。
まとめ 源保堂鍼灸院として読む価値
私たちが東洋医学を通して患者さんと向き合うなかでも、『養生訓』に記されている教えは今なお深く共鳴します。
健康とは「病気にならないこと」ではなく、「日々をどう生きるか」の積み重ね。
若い頃から苦労をしてきた益軒が、最晩年入って到達した境地、そして人生をトータルで俯瞰していく、その深い視点が『養生訓』を読む楽しみの一つでもあります。ところどころに、時代の古さや科学的に否定される部分もありますが、それは時代のなせるものとして多めに見ながら、それよりも最も大切なその本質を抽出して解説していけたらと思います。この連載を通じて、東洋医学的な視点も交えながら『養生訓』を現代語訳・解説し、皆さんの生活に役立つ知恵としてお届けしていきます。
定本として『養生訓・和俗童子訓』(岩波文庫)を使用

源保堂鍼灸院・院長
瀬戸郁保 Ikuyasu Seto
鍼灸師・登録販売者・国際中医師
東洋遊人会・会長/日本中医会・会長/東洋脉診の会・会長
東洋医学・中医学にはよりよく生活するための多くの智慧があります。東洋医学・中医学をもっと多くの方に身近に感じてもらいたい、明るく楽しい毎日を送ってほしいと願っております。
Save Your Health for Your Future
身体と心のために
今できることを
同じカテゴリーの記事一覧