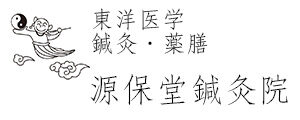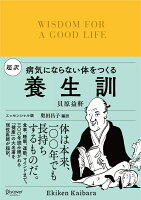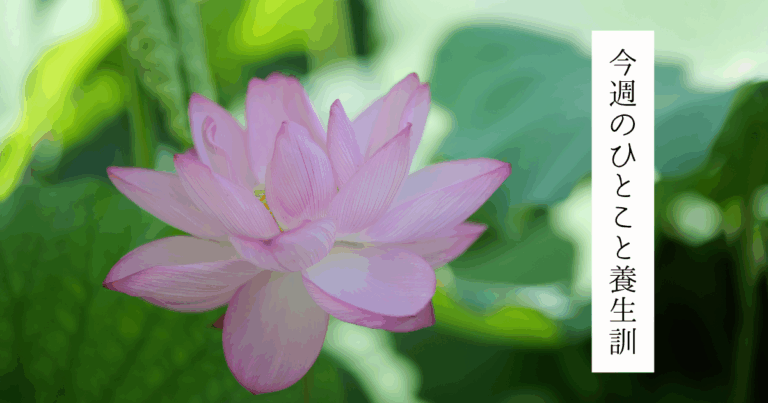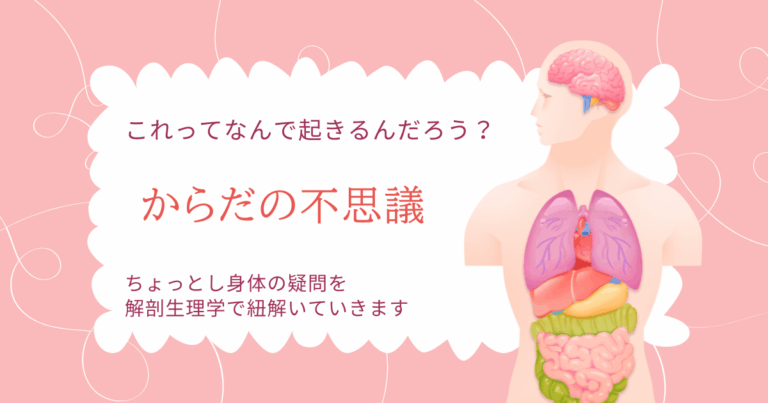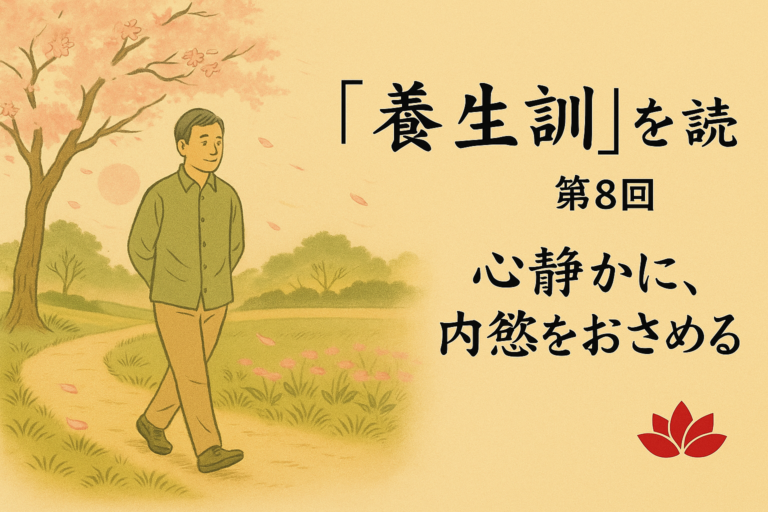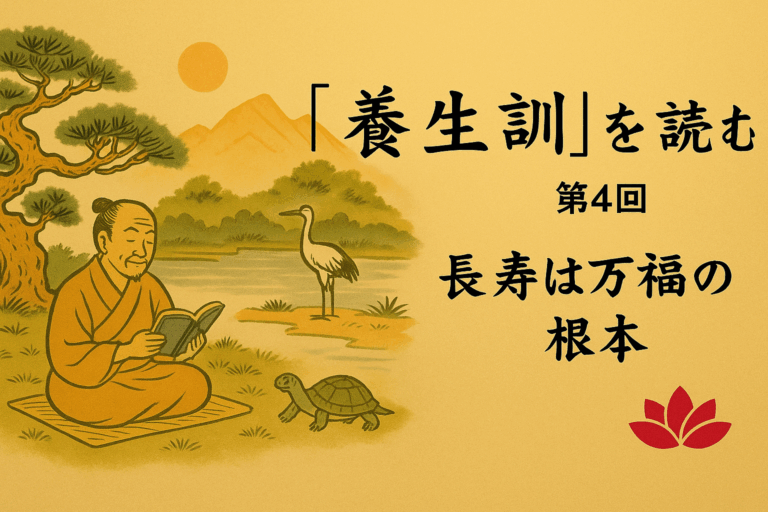『養生訓』を読む 第5回
命は天地父母からの授かりもの
原文(巻之一・総論上・2章)
万の事つとめてやまざれば、必(ず)しるし(験)あり。たとへば、春たねをまきて夏よく養へば、必(ず)秋ありて、なりはひ多きが如し。もし養生の術をつとめまなんで、久しく行はば、身つよく病なくして、天年をたもち、長生を得て、久しく楽まん事、必然のしるしあるべし。此理うたがふべからず。
現代語訳
あらゆることも、努力を続けてやめなければ、必ず成果が現れてきます。
それは、たとえば、春に種を蒔いて、夏にしっかりと養い育ててあげれば、必ず秋になると実りが多く得られるようなものと同じなのです。
もし養生の方法を学び、長く実行すれば、体は丈夫で病気もなく、天から授かった寿命を保ちながら、長生きして、長く楽しむことができるのは、必ず起こる結果です。この道理は、疑うべきものではありません。
解説
養生も、“継続は力なり”
この一節では、「努力を継続すれば必ず成果が得られる」という普遍的な法則を、季節の流れと農作とを絡めながら、養生の実践を説明しています。それは具体的に、春に種をまき、夏に手間をかけて育てれば、秋には必ず実りがあるというもので、養生の実践もまた、続ければ必ず健康と長寿という実を結びます。
季節の流れと農作を絡めたのは、これは、一般の人でもわかりやすくするための例え話という意味だけではなく、実際に、春夏秋冬の季節の巡りと身体のあり方の流れでもあります。春夏秋冬は、それぞれ生長化収蔵というものが割り当てられます。つまり、春は新芽が芽吹く“生まれる”季節であり、夏は葉っぱを広げて増やしていく、“長”の時季。そして秋は“収穫の秋”で、冬はそれらを刈り取って“蔵”に収めます。季節にはそれぞれに働きがあり、それに合わせていくと体も心も順調になるということになります。
やめないこと、続けること
ここで重要なのは「やめないこと」です。
途中でやめれば成果は得られません。
貝原益軒は農作業という身近で具体的な例を挙げることで、この道理を誰にでもわかる形で伝えています。当時の日本、つまり江戸時代は、稲作によって経済が動く米本位制でもありますから、農業による例えは多くの人に伝わったのではないでしょうか。現代の私たちにとっても、お米は日本の主食であり続けていますから、農業の有り難さを身近に感じながら、このお話の意味を汲み取ってみてはいかがでしょうか。
まとめ 源保堂鍼灸院の見解
東洋医学では、身体を養う行為も自然の営みと同じく「積み重ね」が大切だと考えます。自然の中に生かされている私たちの身体と心でありますから、自然と同調するのは当然のことですし、一年一年の成果の積み上がりが人生を豊かにするものです。
季節や気候に合わせて生活を調え、食事や睡眠を整える。これが基本です。
そして自分ではどうにもできなくなったとき、また、疲れやダメージをそのままにして溜めないようにするために、ときには鍼灸などを受けてみるのも、大切な養生になります。。これらは一度や二度ではなく、日々の中で繰り返すことでこそ効果を発揮します。
源保堂鍼灸院には、何はなくとも定期的に受鍼される方が多いのですが、これは私どもが強要しているわけではなく、患者様ご自身がその価値を感じ取って自らそのようなペースにして受鍼されていることがほとんどです。
現代人は即効性を求めがちです。その傾向は昔からで、現在はいわゆるエナジードリンクといったものが幅を利かせているようになってしまいました。
しかし、益軒は300年以上前から「健康の実りは、日々の種まきと手入れによってもたらされる」と説いています。特効薬や一時的なブームに頼らず、自分の生活習慣という畑を豊かに耕す——これこそが養生の王道なのです。
定本として『養生訓・和俗童子訓』(岩波文庫)を使用
『養生訓』に関連する本

源保堂鍼灸院・院長
瀬戸郁保 Ikuyasu Seto
鍼灸師・登録販売者・国際中医師
東洋遊人会・会長/日本中医会・会長/東洋脉診の会・会長
東洋医学・中医学にはよりよく生活するための多くの智慧があります。東洋医学・中医学をもっと多くの方に身近に感じてもらいたい、明るく楽しい毎日を送ってほしいと願っております。
Save Your Health for Your Future
身体と心のために
今できることを
同じカテゴリーの記事一覧