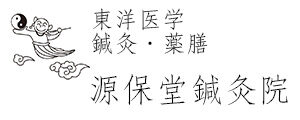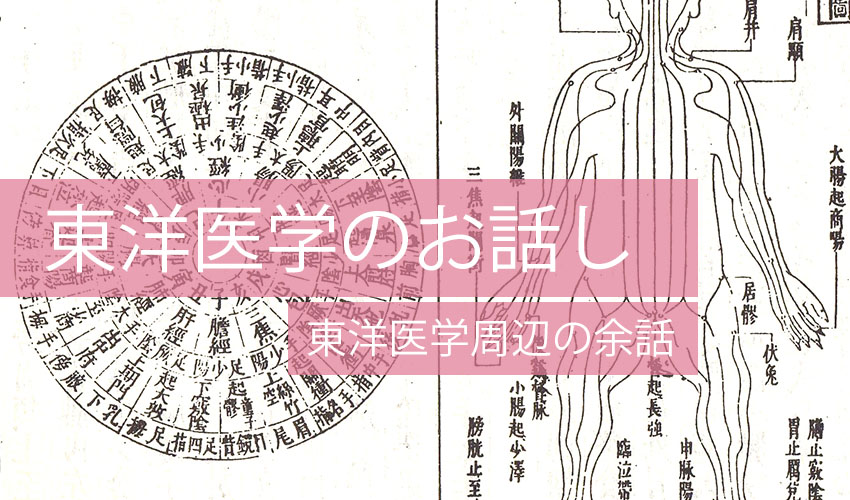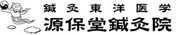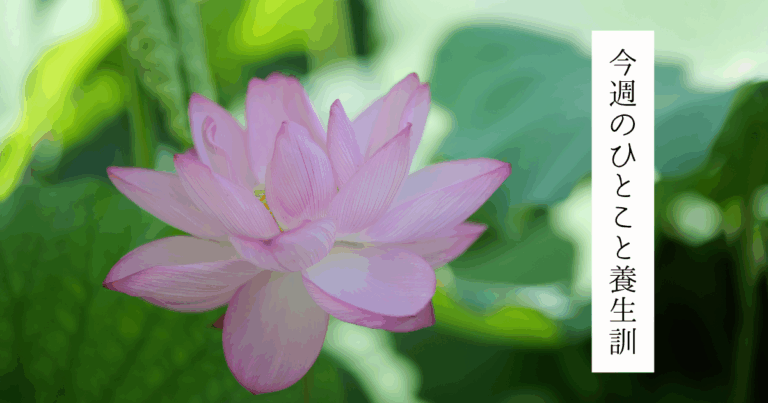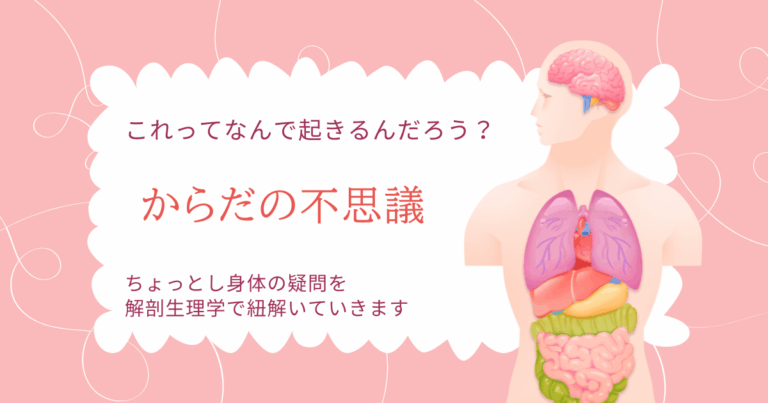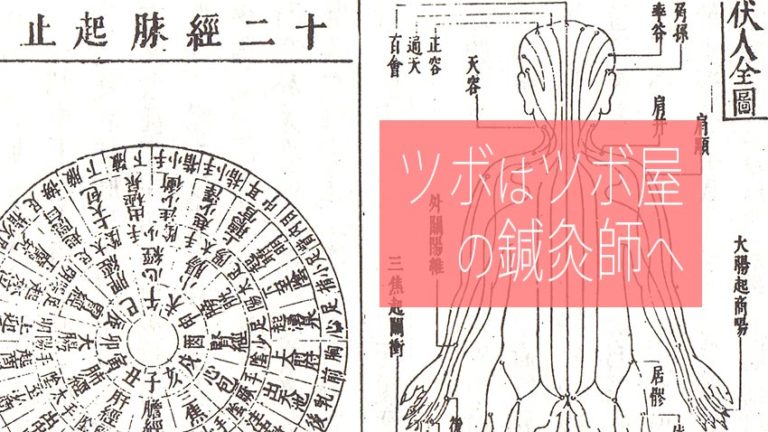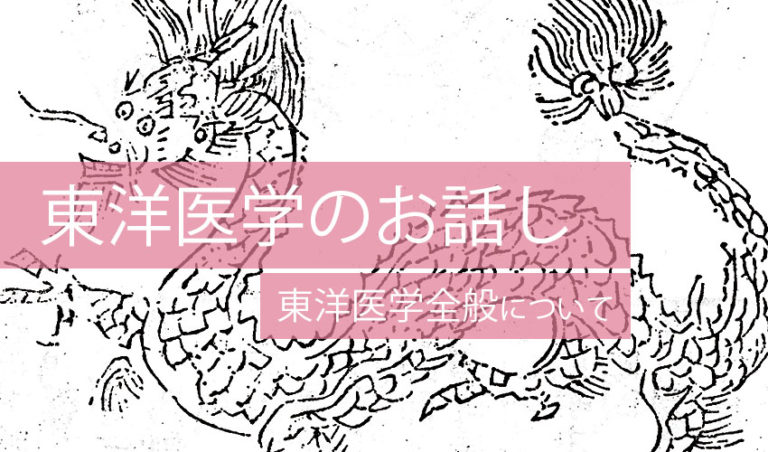東洋医学は曖昧?
本治法をしています
表参道・青山・源保堂鍼灸院で行っている治療は「本治法」といいます。
これは私が発明したものではなく、鍼灸医学の発展とともに確立してきた心身一如の全体調整鍼灸療術です。これは、「五臓六腑の生気の調整」を主眼にして、全体を良くしながら部分をも同時に改善させていくものです。ですので、患部には鍼をしませんし、病名とツボを対応させることもしていません。
鍼灸の世界にはいろいろな考え方を持った方がおり、それぞれ工夫をしたりしながら、それぞれの考え方のもと、それぞれの治療をしている先生方が多いです。いろいろなニーズに合わせて癒しの形があるのだなと思うので、どれも否定をしたりはしません。しかしながら、こと「東洋医学」という言葉を使いながら、その東洋医学の考え方を臨床に活かしていない治療家の方を見ると、少々、いや、かなり一言言いたくなってしまうところもあります。それはまだ私が血気盛んなところがあり、性格的なところに起因していると思いますが・・・。
曖昧なものなのか?
先日ベテランのある先生とこんな会話をしました。
それは、その先生が書いたコラムについて、私が話をしたことに始まります。
私が、「先生のコラム拝見しましたけど、大宇宙の気=六淫となってましたけど、あれは明らかに間違いですよ。あの文脈からしたら、六気とか主気とか言わないと正確ではないですよ。」と言う。
するとその先生は、
「いや、東洋医学の用語は曖昧だから、そんなこと気にしないくていいんだよ。だいたい私は古典はほとんど読んでないしな。」といった。
私は返す言葉もなく、
「あ、そうですか。そんなもんですか・・・。」と私は半ばあきれて口をつぐんでしまった。そのコラムの中で、この先生は「鍼灸師にしか出来ない東洋医学」とも言っていたのに・・。
東洋医学というと、中国の歴史に漂う悠久たる流れ、あるいは太極拳のようなゆったりした動きを連想させるのか、どうやら同業の先生であっても、このように曖昧なものという印象を受けるようだ。言葉の定義もいい加減にして通り過ぎている方が多いように思う。
しかし、東洋医学と、「医学」の名が冠してあるのだから、患者様の健康を預かる身として、曖昧すぎてはいけないのではないだろうか。鍼灸や湯液医学しかなかった時代、医療を受けられのはごく限られた皇帝級の人々だった。もし曖昧にしていい加減な治療をしたとしたら、治療者は皇帝からどんな仕打ちをされたことだろう・・。そうった時代背景を考えてみると、東洋医学は決して曖昧なものではない。問題は古医書をどう解釈していくか、どう臨床に活かしていくかという読み手である術者の力量なのである。
鍼灸医学・湯液の世界でも基本となる古医書の原点『黄帝内経』には、多くの注釈本がある。歴代の名医家達が、より厳密に身体を解釈していこうと試みた大切な遺産である。それを無視して、自分の気分や自分の知識の範囲だけで曖昧といってしまうのはいかがなものかと思う。
その先生は気がついたようにこう言った。
「瀬戸先生、○○病のときはどこのつぼ使うの?参考にさせてよ。」
私は言葉を失った。
「え、いや、どこでしょうね・・・」
何をか謂わん哉、である。
同じカテゴリーの記事一覧

源保堂鍼灸院・院長
瀬戸郁保 Ikuyasu Seto
鍼灸師・登録販売者・国際中医師
東洋遊人会・会長/日本中医会・会長/東洋脉診の会・会長
東洋医学・中医学にはよりよく生活するための多くの智慧があります。東洋医学・中医学をもっと多くの方に身近に感じてもらいたい、明るく楽しい毎日を送ってほしいと願っております。
Save Your Health for Your Future
身体と心のために
今できることを